無料相談受付中
0120-328-710
問い合わせ・相談予約 平日・土日祝日 9:00~17:30
メールでの問い合わせに迅速に対応させていただきます。原則 24 時間以内にお返事いたします。
遺留分侵害額請求を減額するための3つのポイント
遺留分は、遺産に含まれる不動産の評価額を算定した上で、請求されることが通常です。一般的に不動産は遺産において多くの価値を占めることから、不動産の評価を適正に行うことが、遺留分侵害額請求を減額することに最も効果的です。
不動産の評価額は、路線価を修正する方法、公示地価を基礎とする方法、不動産業者の簡易査定を基に主張されることが一般的です。これらの不動産の評価方法自体は、対象不動産の大まかな評価額を固める意味で有効ですが、不動産ごとの特性にあわせて修正が必要な事例もあります。
そもそも、量産できる商品とは異なり、不動産は個別性が高い物件であるため、程度の差はあるにせよ、ここの不動産固有の特徴というものがあります。例えば、地中にガラが存在する、地形が悪い、接道要件を満たさないため再建築ができない等です。
上記のような評価額を減額につながる要素は、遺留分の請求においては除外されているケースが多いため、遺留分侵害額請求を受けた場合、慎重に吟味する必要があります。
遺留分の額を算定する場合、遺産に含まれる積極財産から消極財産(相続債務)を控除することとされています。したがって、遺留減殺請求をされた場合、遺留分算定において、相続債務が適正に控除されているか否かに注意する必要があります。
また、金融機関からの借入等は、融資に関する契約書や確定申告時資料などから容易に判明しますが、相続債務のなかには親族からの借入のため契約書等の書面が存在しないものもあります。このような債務も相続債務に含まれるため、相続債務に計上することで遺留分の額を減額することに繋がります。
(遺留分の算定)
第1029条 遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。
2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。
遺留分侵害額請求をしている相続人が、被相続人から生前に贈与を受けている場合、その贈与が生計の資本としての贈与等にあたり、特別受益として、遺留分額から控除できる場合があります。特別受益と認定されれば、計算上の遺留分額から特別受益とされた贈与の価格を控除することができるので、遺留分侵害額請求を減額する効果があります。特に、特別受益とされる贈与等は、一定程度まとまった金額であることが多いため、遺留分侵害額請求を大幅に減額する効果が望めます。
特別受益は、被相続人と贈与等を受けた相続人という他人間の行為であり、また、一方当事者の被相続人は亡くなっているため、調査は容易ではありませんが、被相続人の通帳・取引明細等を丹念に確認して、事実確認を行うことが重要です。
(代襲相続及び相続分の規定の準用)
第1044条 第887条第2項及び第3項、第900条、第901条、第903条並びに第904条の規定は、遺留分について準用する。
(特別受益者の相続分)
第903条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
遺留分侵害額請求をされた場合、3つの解決方法があります
価額弁償とは、遺留分に相当する金銭を支払うこと遺留分侵害額請求を解決する方法です。遺留減殺請求をされた場合の解決方法としては、最も多く採用されています。
価額弁償の特徴としては、価額弁償するか否かを個々の遺産ごとに判断することができるという点です。したがって、複数ある遺産のうち、単独取得する必要性が高いものについて優先的に価額弁償を行うという方法をとることができます。
また、収益物件について遺留分侵害額請求がされた場合、請求日の翌日以降の賃料は遺留分割合に応じて遺留分侵害額請求をした相続人に帰属することになります。収益物件の賃料額によっては、遺留分侵害額請求後、早期に価額弁償をすることとで、遺留分侵害額請求をした相続人に賃料が帰属することを防止することができます。長期戦が予想される場合は、早めに価額弁償をすることも検討する必要があります。
価額弁償は、価額弁償を行うか否か・その時期、対象の選択等、最終的な解決を見据えて戦略的に行使することが重要です。
(受贈者による果実の返還)
第1036条 受贈者は、その返還すべき財産のほか、減殺の請求があった日以後の果実を返還しなければならない。
(遺留分権利者に対する価額による弁償)
第1041条 受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。
2 前項の規定は、前条第1項ただし書の場合について準用する。
遺留分侵害額請求の交渉をしていると、遺産に含まれる特定の財産を譲渡する方法で解決したいというケースがあります。
遺留分侵害額請求は、理論的には、①遺留分侵害額請求により、遺留分割合に応じて遺産が共有の状態になるため、裁判所の判決で解決をする場合、遺留分割合に応じた共有持分を取得するか、②価額弁償により金銭を受け取るか、という二つの選択肢しかありません。
しかし、遺留分侵害額請求訴訟において和解により解決する場合、遺留分として、特定の遺産全部を取得することが可能になる場合があります。
この方法は、遺留分侵害額請求も『遺産分け』という意味では遺産分割と変わりないという当事者の意識からすると自然に出てくる発想であり、事案の解決という観点からは有効な場合がありますので、積極的に検討すべきでしょう(なお、上記のような理論的な問題もありますので、裁判所、法務局との間で事前に十分な検討が必要になります)。
『共有は、問題の解決にならないことから、共有にするべきではない。』ということは、ほとんど遺留分の実務書に書いてあり、法律相談でもアドバイスされると思われます。一般的にはそのとおりであり、可能な限り、共有は避けることが望ましいです。
しかし、現実には、資金確保の関係で、全部の遺産について価額弁償ができない場合があります。このような場合、遺産を共有にしても当該遺産の共有においてイニシアティブをとれるのであれば、共有を受け入れるという選択肢もあり得ます。
共有物の管理については、民法で持分価格の過半数により決定するとされていますので、当該遺産について遺留分侵害額請求により共有になっても過半数を確保できるのであれば、管理でイニシアティブをとることが可能です。例えば、①収益不動産の管理に関しては、自分を代表者に指定し、共有者の代表者として管理行為を行う、②株式の準共有であれば、自分を権利行使者に定めて会社通知することで、準共有となっている株式全体について議決権などの株主権を行使することができます。
もちろん、共有になることで、他の共有持分権者との煩雑な調整を強いられることがあるため、できれば共有は避けたいところですが、資金の状況や全体の解決枠組みとの関係で、一部の遺産は共有にするという選択肢も検討の価値はあります。
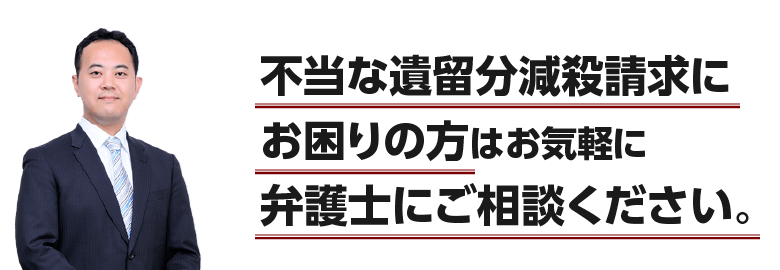
【遺留分請求代理サービス】
遺留分の交渉・裁判手続・遺産の分配まで弁護士が代理します。
着手金 一律 50万円(税別)
成功報酬 20%(税別)
※最低報酬50万円
日当:出廷7回目から1出頭あたり3万円(消費税別)
- 相続人調査
- 遺産調査
- 遺留分算定
- 交渉代理
- 裁判手続代理
- 遺産の解約・名義変更
- 遺産の分配
- 不動産売却
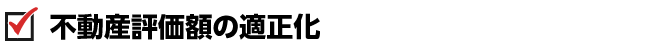



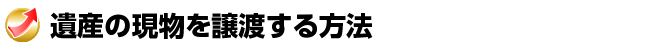

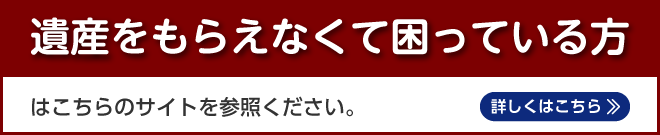
送信できない場合は、メール(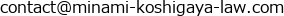 )またはお電話でご連絡ください。
)またはお電話でご連絡ください。
当事務所のプライバシーポリシーはこちらをお読みください。