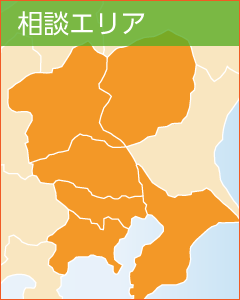相続が発生したことを金融機関が認識すると預貯金が凍結され、入出金ができなくなってしまうことは、相続Q&A【預貯金が凍結される時期】で説明しました。
そこで、今回は、預貯金の凍結を解除する方法と注意点についてご説明します。
〔目次〕
1 相続手続
1
タグ「相続手続き」が付けられているもの
金融機関の一般的な運用として、相続が発生すると、被相続人(亡くなった方のことです)の預貯金を凍結するという対応がとられています。
預貯金が凍結されると、原則、預貯金の出し入れができなくなります(これでビックリして弁護士に相談する方もいます)。
葬儀費用
借金の調査は、相続放棄をするか否かとも関連して重要です。まずは次の資料を確認しましょう。
①故人名義の預貯金通帳
②故人が所有していた不動産の登記事項証明書
③故人名義の自動車の車検証
④故人宛の郵便物
以上の資料から判明した債権者に債務の残高を照会します
最初に次の資料を確保しましょう。
①固定資産税納税通知書(故人の自宅宛に送付されています)
②固定資産税課税台帳(名寄せ帳)
③所得税確定申告書(申告している場合)
次に、上記の資料に記載された不動産の登記事項証明書を法務局で取得します。共同担保目録に固定
金融機関に取引の有無を照会する際、過去に解約された取引についても開示を依頼してください。
解約済みの被相続人の取引について、相続人が取引履歴の開示を求めることを否定した東京高裁の裁判例がありますが、全ての金融機関が解約済みの取引の開示を拒絶しているわけでは
被相続人が取引をしていた可能性が高い金融機関の探しかたとしては以下のような方法があります。
①自宅のカレンダー等をチェックする。
②被相続人が使用していた連絡帳、名刺フォルダをチェックする。
③郵便物をチェックする。
④自宅などの不動産の登記簿謄本を取って
相続で揉めている事案では、一方の相続人が他方の相続人に遺産の内容を開示しないということはよくあります。
このような場合は、弁護士を通して遺産の開示を求めつつ、被相続人が口座を開設していた可能性のある金融機関に口座の有無を照会します。
金融機関からは、照会に
お通夜や葬儀の準備をしてください。その後、各種行政手続を行います。遺産分割協議は、49日法要が終わった頃に行うことが多いようです。
ただし、負債が多額の場合は、相続放棄をする必要がありますので、相続発生後は、故人宛の郵便物や故人の通帳の内容は確認しておきま
1